固定資産税
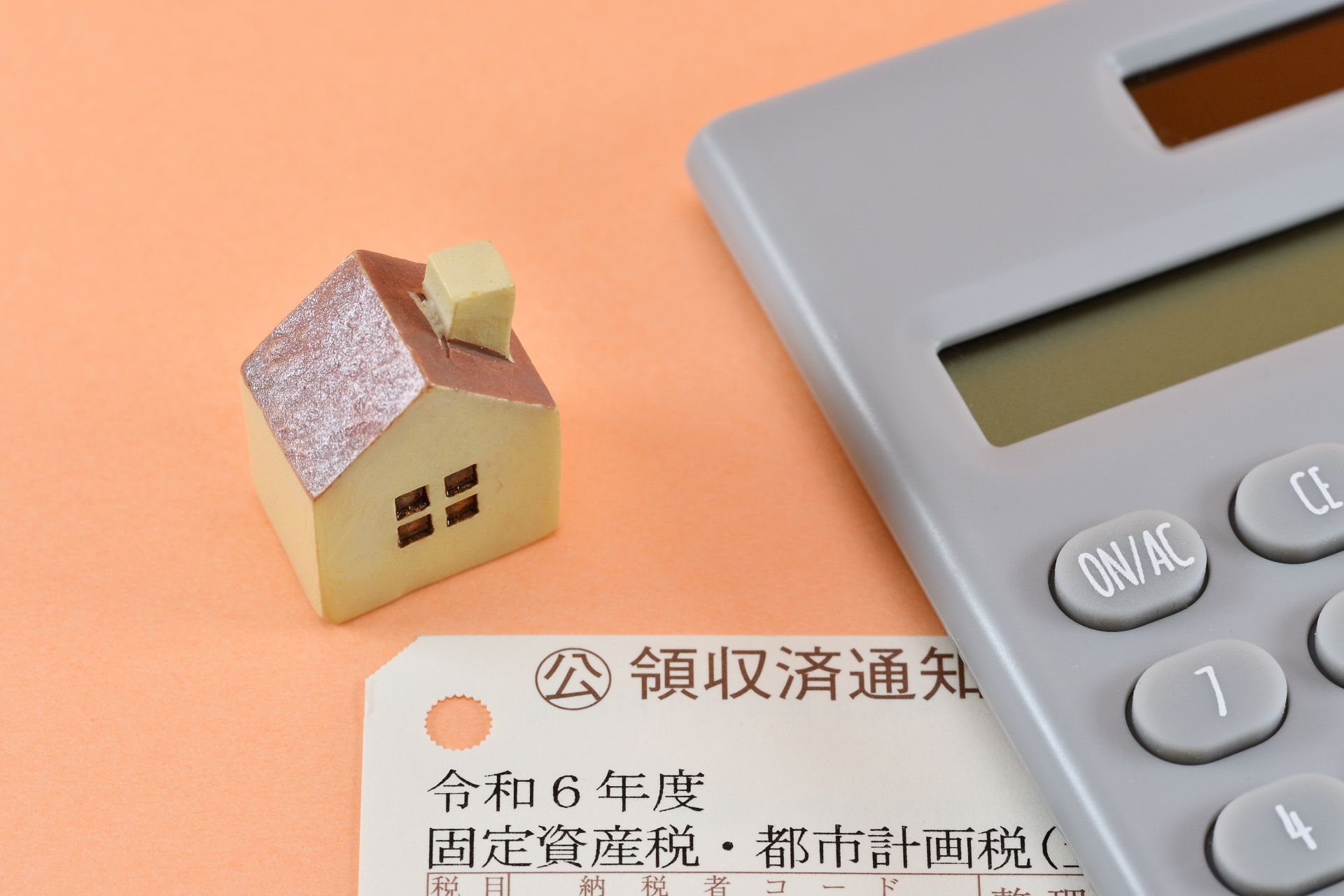
-
都市計画税とは?固定資産税との違いや計算方法、軽減措置を解説
2025.07.4不動産を所有していると、毎年「固定資産税」とともに「都市計画税」という税金が課されるケースがあります。都市計画税は住んでいる地域によってはかからないため、馴染みがなく、意外と知らない落とし穴かもしれません。 この記事では、都市計画税の課税される地域や計算方法などをわかりやすく解説します。軽減措置まで紹介するため、期限内に申請して税負担を軽減してください。 ※本記事に記載されている内容は、2025年7月執筆時点のものです。記事公開以降に、法改正される可能性もありますので、最新情報は不動産を管轄する市区町村や税事務所のホームページなどでご確認ください。 都市計画税とは 都市計画税は、所有している不動産が「都市計画区域内の市街化区域」にある場合に納める税金です。都市計画区域とは、都市計画に基づいて整備・開発・保全する必要があるエリアを指します。都市計画税は、毎年1月1日時点で土地や建物を所有している人が支払わなければなりません。 市区町村(東京都23区内は都)に都市計画税は納められます。道路や公園、上下水道といった都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てられます。 参考:総務省|都市計画税 市街化区域とは 市街化区域とは、すでに街として建物が建ち並んでいる場所や、これから10年以内に積極的に街づくりを進めていく計画がある場所です。商業地域や駅、公園などの施設が整備されているエリアが例として挙げられます。 市街化区域は都市計画法に基づいて、住居や商業、工業などの土地の用途が定められています。 市街化区域に該当するか確認する方法 多くの市町村のウェブサイトでは、都市計画図や用途地域マップを公開しています。インターネットで「〇〇市 都市計画図」などと検索すると、自分の住んでいる地域の地図を確認できる場合があります。 地図が公開されていない場合は、不動産を管理する市区町村の都市計画を担当する部署に問い合わせましょう。 また不動産の購入や売却を検討している場合は、事前に不動産会社に確認してもらうこともできます。 固定資産税との違い 都市計画税と固定資産税の違いは、課税される目的と対象地域、税率です。 固定資産税は、所有している土地や建物といったすべてに対して、全国どこでも課されます。固定資産税の使い道は、地方自治体のさまざまな行政サービス全般です。税率は、原則として固定資産税評価額の1.4%です。 一方、都市計画税は、都市計画区域の中でも特に「市街化区域」にある土地や建物に限定して課されます。都市計画税の目的は、都市の整備や開発を行うための費用をまかなうためです。税率は、原則として固定資産税評価額の0.3%と決められています。 参考:固定資産税|総務省 固定資産税の金額や税率、軽減措置が気になる方は、こちらの記事をご覧ください。固定資産税とは | いつ・どのくらい支払う?計算方法と特例や控除まで 都市計画税の納税方法 都市計画税の納税方法は、納税通知書を銀行やコンビニエンスストアに持参し、現金での支払いが一般的です。 自治体によっても異なりますが、毎年5月頃に固定資産税と都市計画税が合わせて記載された納税通知書が、市区町村(東京都23区内は都)から郵送で送られてきます。 この納税通知書には、4期分の納付書が同封されています。一般的には6月、9月、12月、翌年2月の年4回に分けて支払うケースがほとんどです。支払いを手間だと感じる方は、金融機関で口座振替手続きをしましょう。 都市計画税の計算方法 都市計画税は、以下の計算式で求められます。 都市計画税額 = 固定資産税評価額(課税標準額) × 税率(原則0.3%) 固定資産税評価額(課税標準額)は、土地や家屋の価値を市区町村が定めた基準で評価した金額です。評価額は、毎年送られてくる固定資産税の納税通知書に記載されている「課税明細書」で確認できます。 固定資産税評価額は3年に1度見直されるため、都市計画税の金額も変動します。 固定資産税評価額が1,000万円の土地と2,000万円の家屋を所有している場合の都市計画税を、計算してみましょう。 土地の税額:1,000万円 × 0.3% = 3万円 家屋の税額:2,000万円 × 0.3% = 6万円 合計の税額:3万円 + 6万円 = 9万円 ただし、土地や家屋の状況によっては都市計画税の税額は異なります。正確な税額を知りたい場合は、自治体から送られてくる納税通知書を確認してください。 不動産売却ならテレルームにお任せ 不動産売却は税金だけでなく、買主探しや契約手続きなど、さまざまな専門知識が必要です。もし売却しようと考えているなら、不動産のプロであるテレルームがおすすめです。 テレルームは、豊富な実績とノウハウを持っている不動産会社です。お客様の状況や、所有する不動産に合わせた最適な売却プランを提案します。また初めて売却する方の不安な気持ちに寄り添った対応をいたします。 まずは話を聞いてみる 都市計画税の軽減措置 都市計画税にも、税金の負担を軽くするための軽減措置があります。自治体によっては、独自の軽減措置を実施しているケースも少なくありません。 【全国共通】住宅用地の課税標準の特例 住宅用地の課税標準の特例は、住宅が建っている土地の都市計画税が安くなる制度です。 住宅の敷地になっている土地(住宅用地)の評価額を計算するときに、課税標準額が減額されます。 住宅用地の面積課税標準額の減額される割合200㎡以下の部分(小規模住宅用地)評価額の3分の1200㎡を超える部分(一般住宅用地)評価額の3分の2 たとえば300㎡の住宅用地に建物が建っている場合、200㎡以下の部分は課税標準額の3分の1、200㎡を超える部分の課税標準額は3分の2になります。 特例が利用できる土地は、人が住むことのみを目的とした専用住宅の敷地として使われている土地、あるいは併用住宅の敷地として使われている土地です。 併用住宅とは、人が住む目的以外に店舗やオフィスなどとして利用されている建物です。 住宅用地の課税標準の特例は、特に申請をしなくても自動的に適用されることがほとんどですが、念のため納税通知書や市区町村のウェブサイトで確認してみましょう。 例1【東京23区】耐震化のために建て替え・改修した住宅の減免措置 東京23区内には、耐震化のために建て替え・改修をした住宅に対して都市計画税の減免措置があります。減免される都市計画税の金額と期間は、次の表の通りです。 耐震化の内容減免される都市計画税期間建て替え新築した住宅に課税される都市計画税の全額新たに都市計画税が課税される年度から3年間改修住宅1戸あたり120㎡までの床面積相当分を全額改修を行った翌年度1年間 減免措置の要件は、建て替え・改修した住宅の居住部分の割合が2分の1以上であることや東京23区内に建物があることなどです。 どちらの措置を利用するにも、不動産を管轄する区の都税事務所への申請が必要です。建て替えは新築した年の翌々年の2月末、改修は工事完了後3カ月以内の申請期限が設けられているため、早めに手続きを進めましょう。 参考:耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免(23区内)~住宅の耐震化を支援します | 東京都主税局 例2【横浜市】新築認定低炭素住宅等に係る都市計画税の減額制度 横浜市には、新築された住宅のうち、一定の省エネ基準に適合する住宅の都市計画税を2分の1に減額する制度があります。 一定の省エネ基準に適合する住宅とは、以下の3つの住宅です。 一定の省エネ基準に適合する住宅の種類概要認定低炭素住宅二酸化炭素の排出量を抑えるための対策が施されたと認定を受けた住宅ZEH水準省エネ住宅断熱性能等級5と一次エネルギー消費量等級6を同時に満たす住宅建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合する住宅省エネ基準よりも高いレベルの省エネルギー性能を求める基準をクリアした住宅 2025年7月現在、対象となる住宅は2022年4月1日から2026年3月31日までの間に建築された建物が対象です。都市計画税が減額される期間は、以下のように住宅の種類によって異なります。 住宅の種類減額期間3階建て以上の耐火構造住宅・準耐火構造住宅5年間上記以外の住宅3年間 耐火構造とは、壁や床などが一定の耐火性能を備えた構造です。準耐火構造は、耐火構造に比べて緩やかな基準を満たした構造を指します。 利用するには、新しく都市計画税を納めることになる年度の1月31日までに、一定の省エネ基準に適合する住宅がある区の区役所税務課に、申告する必要があります。2026年度から都市計画税を納める場合の申告期限は、2026年1月31日です。 この記事で取り上げた自治体の特例以外にも、お住まいの地域で減免措置を実施している可能性があるため、不動産を管轄する都道府県のサイトを確認してください。 参考:新築認定低炭素住宅等に係る都市計画税の減額制度 | 横浜市 まとめ 都市計画税とは、毎年1月1日時点で都市計画区域内の市街化区域にある土地や建物を所有している人に課される税金です。市街化区域とは、すでに街として建物が建ち並んでいる場所や、これから10年以内に積極的に街づくりを進めていく計画がある場所を指します。 都市計画税の金額は、固定資産税評価額 × 税率0.3%で求めます。都市計画税の負担が重いと感じた場合は、特例が利用できないか調べてみてください。東京23区や横浜市には、申告すれば都市計画税を軽減できる特例が定められています。 もし都市計画税や固定資産税の負担が高く、不動産の売却を検討している方は、テレルームにご相談ください。 不動産売却ならテレルームがおすすめ 不動産売却は税金や法律、市場の動向など、専門的な知識が必要となる複雑な手続きです。テレルームは不動産のプロフェッショナルであり、売却を0から丁寧にサポートしてくれます。 テレルームの担当者は豊富な実績と専門知識を持っており、あなたの不動産売却に最初から最後まで併走してくれます。売却価格の査定や買い手探し、契約手続き、そして税金に関するアドバイスなど、あらゆる疑問や不安に対応してくれるため、安心して売却を進められるでしょう。 まずは話を聞いてみる











