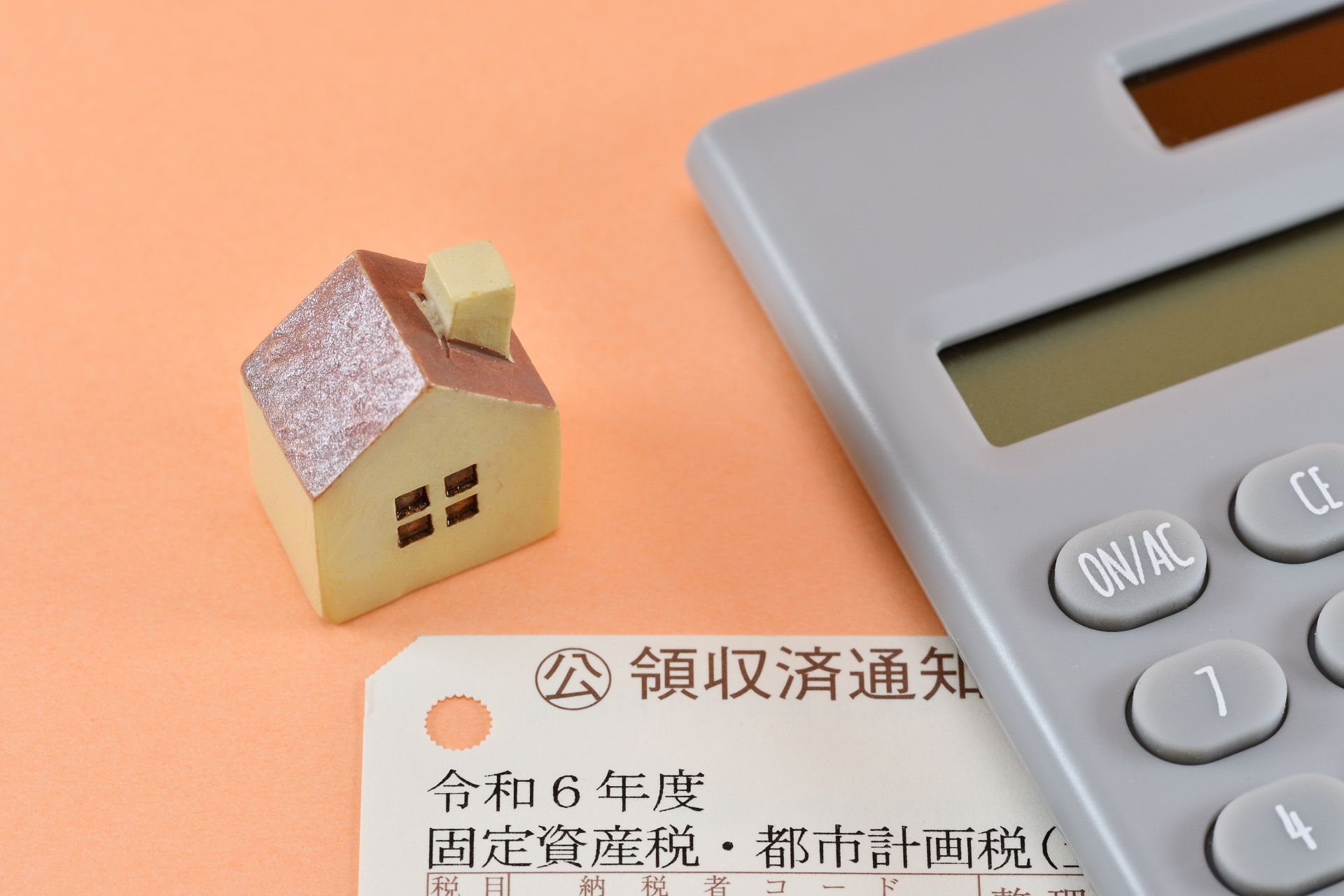テレルーム

-
マンション売却の準備から引渡しまで徹底解説|高く・早く売るためのコツもご紹介!
2025.07.6マンションの売却を検討しているものの「一体いくらで売れるんだろう?」「手続きが複雑そう…」と、お悩みや疑問を抱えていませんか?この記事では、売却の流れや資産価値を最大化して高く・早く売るためのコツ、見落としがちな費用や税金の話まで、わかりやすく解説します。あなたの大切な資産を納得のいくかたちで売却できるよう、ぜひ最後までご覧ください。 【全体像】準備から引渡しまで!マンション売却の流れを把握 マンション売却には、3〜6か月、場合によってはそれ以上の時間がかかります。基本的な流れは、以下のとおりです。STEP1:準備・相場調査(1〜2週間)・住宅ローンの残高を確認・周辺の売却相場をインターネットなどで調べる・売却を依頼する不動産会社の候補をいくつかリストアップSTEP2:査定・媒介契約(1〜2週間)・複数の不動産会社に査定を依頼(訪問査定がおすすめ)・査定価格の根拠や販売戦略を聞き、依頼する会社を決定・不動産会社と媒介契約を結び、売出価格を決定STEP3:売却活動・内覧対応(1〜3か月)・不動産ポータルサイトなどへ物件情報が掲載される・購入希望者からの問い合わせに対応し、内覧の日程を調整・内覧当日は、室内をきれいに整えて購入希望者を迎えるSTEP4:売買契約・引渡し(1〜2か月)・購入申込書を受け取り、価格や条件を交渉・合意・不動産会社にて重要事項説明を受け、買主と売買契約を結ぶ・住宅ローンの残債を完済し、抵当権の抹消手続きを行う・残代金を受け取り(決済)、買主に鍵を渡して物件を引渡す マンション売却の第一歩!「査定」と不動産会社の選び方 マンション売却を考え始めたら、まず「いくらで売れそうか」を把握するための査定をします。査定は、売却の成功を左右する不動産会社選びの第一歩です。 「机上査定」と「訪問査定」どう使い分ける? 査定には2種類あり、目的に応じて使い分けます。・机上査定(簡易査定):物件情報(所在地、築年数、広さなど)や周辺の取引事例をもとに、おおよその査定額を算出。「すぐに売る気はないけど、今の価値を知りたい」「まずは気軽に相場観をつかみたい」という方におすすめ。・訪問査定(詳細査定):不動産会社の担当者が実際に物件を訪れ、部屋の状態、日当たり、眺望、管理状況などを細かくチェックして、より精度の高い査定額を算出。 信頼できる不動産会社の選び方 査定額の高さだけでなく、売却を任せるパートナーとして、信頼できる会社か見極めましょう。・査定価格の根拠が明確か:「なぜこの価格なのか」を、周辺相場や物件のプラス・マイナス点を踏まえて具体的に説明してくれる・売り方の提案が明確か:物件の価値を最大限に引き出す、効果的な方法や時期を教えてくれる・売却実績が豊富か:売却したいマンションのエリアや、同じマンション内での取引実績があると良い・担当者との相性:親身に相談に乗ってくれ、報告・連絡・相談がスムーズ 3種類の「媒介契約」の違いと選び方 売却を依頼する不動産会社が決まったら、「媒介契約」を結びます。契約には3つの種類があり、それぞれの特徴は以下のとおりです。 契約の種類特徴こんな方におすすめ専属専任媒介・依頼できるのは1社のみ・自分で買主を見つけても、その不動産会社を通す必要がある・不動産会社は1週間に1回以上の報告義務がある信頼できる1社にすべてを任せ、手厚いサポートでスピーディに売却を進めたい方専任媒介・依頼できるのは1社のみ・自分で買主を見つける「自己発見取引」ができる・不動産会社は2週間に1回以上の報告義務がある1社に任せたいが、知人や親族に売却する可能性も残しておきたい方一般媒介・複数の会社に同時に依頼できる・自分で買主を見つけられる・不動産会社に報告義務はない(任意)人気エリアの物件で引き合いが多そうな場合や、広く情報を拡散して競争環境を作りたい方 テレルームでは、お客様と一緒にご希望や条件を整理し、安心して進められるようご案内します。マンションの売却をお考えの方は、お気軽にご相談ください。まずは話を聞いてみる マンションを少しでも高く・早く売るための4つのコツ マンションの価値を最大限に引き出し、より有利な条件で売却するための4つのコツをご紹介します。 内覧準備で「住みたい」を演出する 内覧は、購入希望者が物件を直接見て「ここに住みたいか」を判断する重要な機会です。第一印象を良くするために、以下のポイントを意識しましょう。・清潔感:玄関、水回り(キッチン、浴室、トイレ)、窓ガラスは念入りに清掃。・開放感:部屋を広く見せるため、床に物を置かず、不要な家具を移動するなどしてスッキリと。・明るさ:内覧時はすべてのカーテンを開け、照明もつけて室内を最大限に明るく演出。・臭い対策:事前にしっかり換気し、生活臭やペット、タバコの臭いを消す。芳香剤は好みが分かれるため、無香料がベスト。 売却のタイミングを見極める 不動産市場は常に変動しています。一般的に、春(2〜3月)や秋(9〜10月)は、転勤や新生活の準備で人の動きが活発になり、売却しやすい時期です。また、金利が低い時期は購入者のローン負担が軽くなるため、売却に有利に働くことがあります。市場の動向も不動産会社と相談しながら、最適なタイミングを探りましょう。 戦略的な「売出価格」を設定する 査定価格を参考に、最終的な「売出価格」を決めます。ポイントは、値下げ交渉を見越して、あらかじめ少し高めの価格で売り出すことです。ただし、相場からかけ離れた高すぎる価格は、内覧希望者が現れず、売却が長期化する原因になります。不動産会社のプロの意見を参考に、購入希望者の興味を引く価格ラインを設定しましょう。 物件の「魅力」を整理し、伝えられるようにしておく 物件のセールスポイントは、住んでいるからこそわかる魅力を整理し、内覧時に伝えられるようにしましょう。(例)・南向きで日当たりが良い・リフォームしてキッチンが使いやすい・管理組合の運営がしっかりしている・近所の〇〇公園は子どもを遊ばせるのに最適 などテレルームでは、あなたのマンションの価値を最大限引き出し、より良い条件での売却をサポートします。少しでも高く・早く売却したい方は、ぜひ一度お問い合わせください。まずは話を聞いてみる 住宅ローンが残っていても大丈夫?残債がある場合の注意点 住宅ローンが残っていてもマンションの売却は可能です。ただし、売却時には必ずローンを完済し、金融機関が設定した「抵当権」を抹消する必要があります。アンダーローン(売却価格 > ローン残高)の場合売却で得たお金でローンを完済し、残った分が手元に入ります。問題なく売却を進められます。オーバーローン(売却価格 < ローン残高)の場合売却価格だけではローンを完済できないため、不足分を自己資金(貯蓄など)で補う必要があります。自己資金で補えない場合は、「住み替えローン」という方法もありますが、審査が厳しくなる傾向があるため、早めに不動産会社や金融機関に相談しましょう。 マンション売却にかかる費用と税金の知識 マンション売却では、手元にお金が入ってくるだけでなく、諸費用や税金といった支出も発生します。売却益を正確に把握するためにも、事前にしっかり理解しておきましょう。 売却時にかかる「諸費用」 諸費用の合計は、売却価格の4〜6%程度が目安です。・仲介手数料:不動産会社へ支払う成功報酬(上限:売却価格×3%+6万円+消費税)・印紙税:売買契約書に貼付する印紙の代金で、売却価格により異なる・抵当権抹消登記費用:住宅ローンを完済し、抵当権を抹消するための手続き費用・その他:必要に応じて、ハウスクリーニング代、引越し費用などテレルームでは、条件によって仲介手数料0円が実現します。諸費用を賢く抑えたい方は、ぜひ一度、テレルームまでご相談ください。 まずは話を聞いてみる 忘れないで!固定資産税・都市計画税の日割り精算 固定資産税や都市計画税は、その年の1月1日時点の所有者に対して、1年分の納税通知書が送られてきます。年の途中で売却した場合でも、法律上の納税義務は売主にあります。実際の不動産取引では、物件の引渡し日を基準に税額を日割り計算し、買主が負担すべき分を売主へ支払うのが一般的です。 「譲渡所得税」の軽減には確定申告が必要 マンションを売却して利益(譲渡所得)が出た場合、利益に対して「譲渡所得税」がかかります。譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)※取得費:物件の購入代金や購入時の諸費用から、建物の減価償却費を引いたものただし、マイホームの売却には税金の特例があります。代表的なものが「3,000万円の特別控除」で、譲渡所得から最大3,000万円を差し引くことができます。つまり、利益が3,000万円以下であれば、譲渡所得税はかかりません。この特例を利用するには、確定申告が必要です。適用条件など、詳しくは不動産会社や税務署に確認しましょう。 戦略的なマンション売却で資産価値を最大化! マンション売却は、ただ手続きを進めるだけでなく、資産価値を引き出す計画が欠かせません。信頼できる不動産のプロに相談することで、納得のいく売却を進められます。 マンションの売却をお考えなら、まずはテレルームへ! マンション売却でお悩みなら、数多くの売却を成功に導いてきたテレルームにご相談ください。・お客様の大切な資産の価値を最大化する売却戦略をご提案・豊富な実績とデータに基づく的確な査定と価格設定・売却活動から引渡し、確定申告のアドバイスまで責任をもってフルサポート売却を決めた方はもちろん、「まずは査定だけしてみたい」「売るか貸すか迷っている」といった段階でのご相談も大歓迎です。テレルームがあなたのスムーズな住み替えをサポートいたします。まずは話を聞いてみる

-
初めてのマンション購入でも安心|情報収集から入居まで徹底解説!
2025.07.5初めてのマンション購入では、「何から始めればいいかわからない」「失敗したくない」といった不安を感じる方も多いのではないでしょうか。この記事では、情報収集からご入居までの流れを、各場面でのポイントやコツとともに、わかりやすく解説します。予算の立て方や住宅ローンの選び方、理想の物件と出会うためのヒント、契約前のチェックポイントなど、あなたの住まい選びにお役立てください。 【全体像】情報収集から入居まで!マンション購入の流れ マンション購入には、3〜6か月ほどの時間がかかります。全体の流れを把握することで、余裕をもって準備を進められ、スケジュールも立てやすくなります。• STEP1:準備・資金計画(1〜2週間)予算設定、希望条件の整理• STEP2:物件探し・内見(2〜8週間)物件情報の収集、内見• STEP3:申し込み・契約(3〜5週間)購入申し込み、住宅ローン事前審査重要事項説明、売買契約、住宅ローン本審査• STEP4:融資実行・引渡し(3〜4週間)住宅ローン契約、決済、物件引渡し マンション購入の予算と資金計画の立て方 マンション購入を考え始めたら、まず取り組みたいのが予算決めです。無理のない資金計画を立てるために、「頭金」「月々の返済目安」「諸費用」の3つのポイントを押さえておきましょう。 頭金はいくら必要?「頭金ゼロ」で購入は可能? 頭金ゼロでローンを組むことも可能ですが、毎月の返済額や支払う利息の総額が増えるため注意が必要です。物件価格の2〜3割程度の頭金を用意できると、無理のない返済計画を立てやすくなります。 ライフイベントも考慮!年収ごとの借入額の目安 年収別の借入額の目安は以下のとおりです。※金利1%、35年返済、返済負担率25%程度を想定 年収借入総額月々返済額400万円約2,800万円約8万円500万円約3,500万円約10万円600万円約4,200万円約12万円700万円約4,900万円約14万円 住宅ローンは20〜35年と長く続きます。その間に起こりうる転職や出産、お子さまの教育費、両親の介護といったライフイベントも考えながら、返済計画を立てましょう。 物件価格だけじゃない!「諸費用」の内訳と相場 マンション購入時には、物件価格とは別に諸費用が必要です。原則として現金で用意しますが、金融機関によってはローンに組み込める場合もあります。目安は中古マンションで物件価格の6〜9%、新築マンションで3〜5%ほどです。なかでも高額になりやすいのが仲介手数料です。(上限:物件価格×3%+6万円+消費税)5,000万円の物件の場合、仲介手数料は約172万円になります。テレルームでは、条件によって仲介手数料0円が実現します。初期費用を賢く抑えたい方は、ぜひ一度、テレルームまでご相談ください。 まずは話を聞いてみる マンション購入で失敗しない住宅ローンの選び方 住宅ローンは、どこでどのような商品を借りるかで条件が大きく変わります。後悔しないためにも、「金利タイプ」「団信」「借入先」の3つは慎重に検討しましょう。 「変動金利」と「固定金利」自分に合うのはどっち? 住宅ローンの金利には、市場の状況によって金利が変わる「変動金利」と、借入時の金利が完済時まで変わらない「固定金利」の2つのタイプがあります。変動金利が向いている方• 世帯年収に余裕があり、金利上昇にも対応できる• 借入額が少ない、または短期間での完済を予定している• 金利動向などのチェックが苦にならない固定金利が向いている方• 将来の金利の動きにハラハラしたくない• 毎月の返済額を確定させ、計画的な家計管理をしたい• 借入額が大きい、または返済期間が長い2つの金利タイプのメリット・デメリットについて詳しく知りたい方は、ぜひこちらの記事もご覧ください。▶住宅ローンで7割が選ぶ「変動金利」とは? 選ぶ前に知るべき特徴とリスク対策▶金利が上昇する今こそ知りたい「固定金利」とは?メリット・デメリットや賢い活用方法を解説! 団体信用生命保険(団信)も要チェック 団体信用生命保険(団信)は、住宅ローンの契約者の「もしも」に備えるための保険です。死亡または高度障害状態になった場合に保険金が支払われ、残りの住宅ローンが全額完済されます。金融機関によってさまざまな保障が選べるため、団信への加入を機に生命保険を見直せば、月々の保険料を抑えられる可能性があります。団信の仕組みや賢い活用方法はこちらの記事でご紹介していますので、ぜひご活用ください。▶団体信用生命保険(団信)とは?住宅ローンの「もしも」に備える仕組みや、契約前に確認したいポイントを解説 どこで借りる?ネット銀行・メガバンク・地方銀行 金融機関の種類メリットデメリットこんな方におすすめネット銀行・金利が低い・手続きがオンラインで完結・対面相談ができない・自己管理能力が求められる金利を最優先し、手続きの手間を省きたい方メガバンク・高い信頼性と安心感・全国に支店があり便利・金利は比較的高め・審査が厳格な傾向大手の安心感を重視し、対面で相談したい方地方銀行・地域密着で相談しやすい・柔軟な審査が期待できる・金利は高め・サービス提供エリアが限定される地元の物件を購入し、担当者と親身な関係を築きたい方 賢いマンション購入のチェックポイント 10年後も20年後も「この家で良かった」と思える、賢い選択のポイントをご紹介します。 資産価値が下がりにくい物件を選ぶ 資産価値の高いマンションは、将来売却や賃貸に出す際に有利なだけではありません。万が一の際も購入時と近い価格で売却できれば、住宅ローンを完済しやすく、経済的なリスクを抑えられます。単なる「住まい」としてだけでなく、将来のあなたを支える「資産」にもなるのです。資産価値が下がりにくい立地の条件• 駅徒歩10分以内、複数路線利用可能• 都心部や主要駅へのアクセスが良好• 再開発計画など、将来性のあるエリア• スーパーや病院、学校などが近くにそろっている 「新築マンション」と「中古マンション」を徹底比較 比較ポイント新築マンション中古マンション設備・内装設備や機能が最新で、誰も使っていないきれいな状態数年で交換や修理が必要な場合がある購入時の確認モデルルームでの確認が中心で、実際の部屋は見られないことも実際の部屋や日当たり、眺望を直接チェックしてから決められる安心・保証法律で定められた長期保証など、アフターサービスが手厚い管理組合の運営状況や修繕履歴を確認することが大切選択肢販売されるエリアや時期が限定されやすい希望のエリアで物件を探しやすく、選択肢が豊富注意点住み始めると価格が下がりやすい傾向購入後すぐの大規模修繕や、修繕積立金の値上げがないか確認 中古マンションの魅力や、購入前に知りたい注意点などを、こちらの記事でご紹介しています。▶中古マンション購入で失敗しない完全ガイド|メリット・デメリットから賢い資金計画、内見のポイントまで徹底解説 内見でココを見よ!「管理状態」「間取り」「共用部」 内見はパッと見の印象だけではなく、実際の生活をイメージしながらチェックしましょう。建物全体・エントランスはきれいか・掲示板の内容(管理組合の活動状況がわかる)・駐輪場や駐車場は整頓されているか室内・日当たり(時間帯を変えて確認できるとベスト)・キッチンやトイレ、お風呂の臭いや水圧・収納の広さやコンセントの位置・数・周りの音は気にならないか共用部・ゴミ置き場はきれいに管理されているか・廊下や階段の状態はどうかテレルームでは、お客様の物件選びを、不動産のプロの視点でサポートいたします。いつでもお気軽にご相談ください。まずは話を聞いてみる 見落としがち!マンション購入後に必要なお金と手続き 「マンションを購入したら支払いは住宅ローンだけ」ではありません。ローン以外にもさまざまな費用や手続きが必要です。 毎月の支出「管理費」「修繕積立金」 「管理費」は、エレベーターの電気代や共用部の掃除費など、マンションの日常運営にかかる月々の費用です。一方、「修繕積立金」は、将来の外壁塗装など大規模な修繕のために積み立てていく費用です。どちらもマンションの快適さと資産価値を保つために欠かせません。 忘れず納税「固定資産税」「不動産取得税」 「固定資産税」は、毎年1月1日にその不動産を所有している人にかかります。中古物件を購入した場合は、売主と買主が日割りで負担するのが一般的です。固定資産税の額は建物の評価額をもとに決まるため、評価額の減少に伴い、固定資産税も少しずつ安くなる傾向があります。「不動産取得税」は、不動産の購入・新築時に、一度だけかかる税金です。これらの税金は住宅ローンとは別に用意する必要があるため、不動産購入の際はあらかじめ資金計画に組み込んでおくと安心です。 賢く節税「住宅ローン控除」 住宅ローンの残高に応じて所得税や住民税が軽減される「住宅ローン控除」は、自動的に適用されるわけではありません。初年度は確定申告が必要となるため、忘れず手続きを行いましょう。• 1年目:確定申告(2月16日〜3月15日)• 2年目以降:年末調整または確定申告• 必要書類:住宅ローンの年末残高証明書、登記事項証明書など 出典:国土交通省「住宅ローン減税」 後悔しないマンション購入は、信頼できるパートナー選びから マンション購入は資金計画から物件選び、契約、購入後の手続きまで、やることが盛りだくさんです。専門的な知識が必要な場面も多く、手探りのまま進めてしまうと後悔につながります。そんなとき、頼りになるのが不動産のプロです。 マンションの購入ならテレルーム! マンション購入でお悩みなら、数多くのマンション購入をサポートしてきたテレルームにご相談ください。・お客様一人ひとりに合わせた資金計画のご提案・プロの目線での物件選びと内見同行・住宅ローン選びから契約手続きまで完全サポート購入を決めた方だけでなく、購入を迷っている段階でのご相談も大歓迎です。テレルームがあなたの住まい探しをサポートいたします。まずは話を聞いてみる

-
一人暮らしに必要な準備はこれで完璧|費用と手続き、賃貸物件選びのポイントも解説
2025.01.31進学や就職をきっかけに初めての一人暮らしを始める方は、新生活への期待と同時に、様々な不安を抱えているのではないでしょうか。この記事では、一人暮らしを始めるにあたって必要な準備を、賃貸契約から引越し、入居後の手続きまで、わかりやすく解説します。一人暮らしの賃貸物件を選ぶポイントもご紹介しますので、お部屋をお探しの方は、ぜひごらんください。 一人暮らしの準備|必要な費用 一人暮らしを始める前には、まとまった資金が必要です。主な費用は、賃貸物件契約、引越し、家具家電の購入の3つです。特に賃貸契約の初期費用は大きな出費となるため、計画的な準備が欠かせません。それぞれの具体的な金額と、賢く準備を進めるためのポイントをご紹介します。 賃貸物件契約 賃貸物件契約には、以下の費用がかかります。 ・敷金:家賃の1~2か月分 ・礼金:家賃の1~2か月分 ・仲介手数料:家賃の1か月分 ・前家賃:入居月の家賃 ・共益費:入居月分 ・火災保険料:年間1万円前後 ・鍵交換費用:1~2万円程度 これらの費用は、物件によって発生しないこともあり、特に敷金・礼金は、一方もしくは両方ない物件も多くあります。物件探しの際は、月々の家賃だけでなく、これらの初期費用も含めて検討することで、予算に応じた選択が可能です。仲介手数料は通常、家賃1か月分必要ですが、不動産会社によって料金設定が異なります。テレルームでは、仲介手数料無料の物件を多く取り扱っているため、初期費用を抑えたい方はお気軽にご相談ください。 まずは話を聞いてみる 引越し 単身者の引越し費用は、関東圏内での引越しの場合、7~10万円程度が目安です。しかし、この金額は引越しの距離や時期、荷物量によって大きく変動する可能性があります。3月から4月は、進学や就職に伴う引越しが集中するピークシーズンとなるため、料金が通常より2~3割ほど割高になることも珍しくありません。引越し費用を抑えるためには、ピークシーズンを避けるか、平日や早朝、夜間の時間帯を選ぶことで、割引などのサービスが受けられる場合があります。引越し業者によって料金設定や付帯サービスが異なるため、複数社から見積もりを取得するのがおすすめです。テレルームでは、引越し業者の提案から契約まで無料で代行可能で、お客様の条件に合わせた最適な業者選定をサポートしています。 家具家電の購入 新生活のスタートに必要な家具家電は、基本的なものだけでも20~30万円程度の予算が必要です。冷蔵庫や炊飯器は一人暮らし用のコンパクトなものもありますが、「容量が足りない」「すぐに買い替えが必要になった」という例もあります。長く使う予定のものは、生活スタイルの変化も考慮しサイズを選びましょう。冷蔵庫、洗濯機、ベッドなどの大型家電や家具は、購入前に必ず確認すべきことがあります。 ・部屋の間取りと設置スペース :家具家電を快適に使用できる十分なスペースがあるか ・搬入経路(エレベーター、階段、玄関) : 大型家具や家電が無理なく運び込めるか これらの確認を怠ると、せっかく購入した家具や家電が部屋に入らないといったトラブルの原因になります。築年数が経った建物の場合、エレベーターのサイズや廊下の幅が現代の標準的な家具や家電の搬入に適していない可能性もあるため、事前の確認が大切です。 一人暮らしの準備|入居前後の手続き 一人暮らしを始める際は、想像以上に多くの手続きが必要です。住所変更やライフラインの契約は、日常生活に直接影響するため、漏れがないよう慎重に進めましょう。ここでは、必要な手続きの詳細と、効率的に進めるためのポイントを解説します。 各種住所変更手続き 住所変更の手続きは、必要書類や手続き先が多岐にわたります。これから説明するものを上から順番に行うと、次の手続きに必要な書類が揃いスムーズです。 ・市区町村での住民票の移動 転出届は引越しの14日前から提出できます。マイナンバーカードを持っている場合、オンラインでの申請も可能です。新たな居住地で提出する転入届は、引越し後14日以内に手続きが必要です。こちらはオンライン申請不可で、市区町村窓口へ提出が必要ですので、ご注意ください。また、国民健康保険に加入している場合は、保険証の切り替えも忘れずに行いましょう。 ・運転免許証の住所変更 新住所地を管轄する警察署で行います。本人確認書類として運転免許証を使用する機会が多いため、できるだけ早めに済ませておくのがおすすめです。手続きには、現在の運転免許証と新住所が確認できる書類(住民票や公共料金の請求書など)が必要です。 ・銀行やクレジットカードの住所変更 住所変更をオンラインで手続きできる金融機関が増えています。メインバンクやよく使用するクレジットカードは優先的に手続きを行い、重要な書類が確実に届くようにしましょう。手続きには、新住所が記載された本人確認書類が必要な場合があります。 ・郵便局の転居届 郵便局の「転居・転送サービス」は1年間旧住所宛ての郵便物を新住所に転送してもらえる便利なサービスです。この手続きは、郵便局の窓口・郵送・インターネットのいずれかで行います。引越し予定日の2週間前から申請可能ですが、引越し後の手続きでも問題ありません。住所変更の手続きが漏れているところからの郵便物も転送されるため、重要な書類の紛失を防げます。 電気ガス水道などライフラインの契約 ライフラインの契約は、新生活を始めるにあたって欠かせない準備です。電気・ガス・水道は、入居日から使用できるよう、事前に契約手続きを済ませておく必要があります。このなかでもガスの契約は、事前予約が必要な場合が多く、開栓作業には立ち会いが必要です。休日は予約が取りにくいため、早めに手配するのがおすすめです。電力会社は、2016年の電力小売全面自由化により、地域の電力会社だけでなく、新電力(小売電気事業者)からも選べるようになりました。割引やポイント還元など、お得なサービスを提供している会社も多く、比較検討することで固定費の削減にもつながります。テレルームでは、これらのライフライン契約をまとめてサポートする無料コンシェルジュサービスを提供しています。初めての一人暮らしでも安心してお任せください。経験豊富なスタッフが、お客様の状況に合わせて最適なプランをご提案し、手続きをサポートさせていただきます。 まずは話を聞いてみる 一人暮らしの賃貸物件選びのポイント 一人暮らしの物件選びは、家賃や初期費用だけでなく、安全面や生活環境、通勤・通学の利便性など、見るべき部分が多くあります。初めての一人暮らしでは気付きにくいポイントも多いため、以下で失敗しない物件選びのポイントを解説します。 初期費用を抑えられるか 一人暮らしのスタートには、賃貸契約や引越し、家具家電の購入など、想像以上に費用がかかります。このなかでも工夫次第で抑えやすいのが賃貸契約の初期費用です。敷金・礼金なしの物件や仲介手数料無料の物件を探してみましょう。テレルームでは仲介手数料無料の物件を多数取り扱っています。家賃1か月分相当の費用を節約できれば、理想のお部屋作りに向けた予算に回すことも可能です。 周辺環境に問題がないか 周辺環境は、日々の生活の質に直接影響するため、内見時にあわせて確認しましょう。繁華街近くの物件は、夜間の騒音や明るさが気になる場合があるものの、飲食店や商業施設が徒歩圏内にあり、買い物や食事に便利な環境です。一方で、閑静な住宅街にある物件は、夜間の人通りが少なく暗い印象を受けることもあります。しかし落ち着いた雰囲気で静かに過ごしたい方にはおすすめです。あなたの今後の暮らしに、どちらが適しているかをイメージしながら選びましょう。 また、日常生活に必要な施設へのアクセスも確認したいポイントです。スーパーマーケットやコンビニエンスストア、ドラッグストア、病院などが徒歩圏内にあると、生活がより便利になります。 セキュリティや防犯に問題がないか オートロックを備えた物件は、入居者以外の立ち入りを防げるため、一人暮らしの方に人気です。また、2階以上の物件は外から覗かれにくくなるため、安心して過ごせます。インターホンにモニターが付いている物件も安心です。最近では、スマートフォンと連携したインターホンシステムも増えており、外出先からでも来訪者の確認や応対が可能な物件も出てきています。通勤や通学に使う道は、夜間の人通りや街灯の明るさをチェックしておきましょう。人通りのない暗い道は、防犯上のリスクが高まります。 家賃は適正か 手取り収入の3割程度を目安にすると、光熱費や食費などの生活費と合わせて無理のない家計を維持できます。家賃は毎月の支出の中で大きな割合を占めるため、慎重に検討しましょう。 事前準備で一人暮らしのスタートも安心! 初めての一人暮らしには、期待と同時に様々な不安がつきものです。この記事で紹介した、一人暮らしに必要な費用と手続きの準備を計画的に進めることで、安心して新生活をスタートできます。特に初期費用は、賃貸物件契約時、引越し費用、家具家電の購入費用まで、様々な支出が重なります。事前に十分な準備期間を設け、余裕を持った資金計画を立てることが大切です。 賃貸契約と暮らしの準備はテレルームにおまかせ テレルームは、一人暮らしをトータルでサポートしています。物件探しからライフライン契約手続きのサポート、引越しの段取りまで、経験豊富なスタッフがお手伝いいたします。また、仲介手数料無料の物件を多数取り扱っているため、初期費用を抑えた物件探しも可能です。遠方にお住まいの方は、完全オンラインでのご案内も行っています。初めての方でも、安心して一人暮らしをスタートできますので、テレルームにお気軽にご相談ください。 まずは話を聞いてみる

-
2人暮らしの賃貸で失敗しない!間取り・家賃・設備のポイントを解説
2024.12.262人暮らしを始めるカップルや夫婦にとって、賃貸物件選びは大切な選択の一つです。快適に過ごすために、間取りや設備・家賃・予算などは、お互いの生活リズムや希望を考慮する必要があります。この記事では、2人暮らしで納得のいく部屋選びのポイントを詳しく解説していきます。今後、2人暮らしを考えている方は、ぜひ参考にしてください。 2人暮らしの賃貸でおすすめの間取り 2人で暮らすためには、それぞれの生活リズムや趣味、仕事スタイルに合わせた間取りを選ぶことが大切です。2人の時間と個人の時間のバランスが取れる間取りを選ぶと、より快適な生活を実現できます。 1DK・1LDK:一緒に過ごす時間を大切にしたい方向け 一緒に過ごす時間を大切にしたい方は1DK・1LDKがおすすめです。お互いのことが見えやすい間取りでありながら、リビングと寝室を分けられるメリットがあります。例えば、パートナーが早く就寝しても、リビングでゆっくり過ごせます。他にも以下のような点が魅力です。 ・2DK・2LDKと比べて家賃を抑えられることが多い ・広すぎない空間のため、掃除や整理整頓の手間がかからない ・1人暮らしに多い1Kと比べ、2人分の荷物も収納できる 2DK・2LDK~:それぞれの時間も大切にしたい方向け それぞれの時間も大切にしたい方は、2DK・2LDK以上の間取りがおすすめです。個人の部屋が確保できるだけでなく、生活スタイルの変化にも対応しやすくなります。将来荷物が増えても、間取りに余裕があると安心です。2DK・2LDKは、以下のような使い方ができます。 ・子どもが生まれた際の育児スペースや、在宅ワークの増加に対応できる ・親族や友人が訪れた際の宿泊スペースとしても使える ・書斎や作業部屋など、仕事や趣味に使える個室を確保できる 間取りを選ぶときは、単に部屋数だけでなく、各部屋の広さや配置にも注目しましょう。2人で内見に行き、それぞれの視点で生活のしやすさを確認するのがおすすめです。部屋を実際に見学することで、2人での生活をより具体的にイメージできます。 2人暮らしの家賃を決めるポイント 2人暮らしは間取りだけでなく、家賃も生活設計の重要な要素です。お互いが無理のない生活を送れるよう、以下3つのポイントを確認しましょう。 1.収入に対して適正な家賃設定か? 2人の手取り収入合計の25~30%を目安に設定しましょう。例えば、手取り合計40万円の場合、家賃は10~12万円が目安です。この際、ボーナスや残業代などの変動収入は含めず、固定収入のみで計算することが大切です。将来的な支出の増加も考慮し、できるだけ余裕を持った設定にしましょう。 2.固定費・生活費はどれくらいかかるか 月々の家賃に加えて、共益費・管理費や光熱費・食費などの生活費がかかります。これらの合計額も考慮に入れたうえで、生活に無理のない家賃を設定しましょう。 3.将来設計の考慮 将来的な転職や結婚・出産などのライフイベントによる環境の変化も忘れてはいけません。特に長く住むご予定なら、今後の生活費の変化も考えて、家賃は少し余裕を持った設定にしておくと安心です。 2人暮らしの賃貸を選ぶときのポイント 賃貸物件を選ぶ際、特に立地・周辺環境・設備の3点は、快適な2人暮らしを実現するうえで大切です。ここでは、それぞれ見るべきポイントをご紹介します。 通勤・通学の利便性を考えた立地選び 立地選びでまず考慮すべきは、それぞれの通勤の利便性です。両方の職場の中間地点は1つの候補ですが、いずれかの職場に近い場所が選ばれるケースも多くあります。その場合は、通勤時間が長くなる方への配慮として、家事分担や家賃負担の調整など、生活面でのバランスを取ることが大切です。将来的な転職や異動の可能性も考慮に入れましょう。複数の路線が利用できる主要駅周辺であれば、さまざまな方面へのアクセスが良く、環境の変化にも対応しやすくなります。 周辺環境 心地よく暮らすためには、お部屋の条件だけでなく、周辺の環境も見ておきたいポイントです。普段の生活に便利な場所かどうか、次のような施設がそろっているかチェックしてみましょう。 ・買い物環境:スーパーマーケット・コンビニの距離 ・医療施設:総合病院・歯科医院・内科医院・ドラッグストアの有無 また、飲食店や商業施設が充実していると、休日の過ごし方の選択肢が広がります。 設備とセキュリティ 毎日の暮らしを快適に、そして安心して過ごすために、お部屋の設備やセキュリティは重要です。人気が高い設備には以下のようなものがあります。 ・防犯面:オートロック・防犯カメラ・2階以上 ・生活設備:バストイレ別・二口コンロ・独立洗面台・室内洗濯機置き場 ・収納設備:ウォークインクローゼット・シューズボックス ただし、これらの設備が全てそろう物件は少ないため、優先順位をつけるとお部屋探しがスムーズに進められます。例えば、料理が趣味の場合は広めのキッチンや二口コンロを重視し、持ち物が多い場合は、各部屋の広さや収納設備が充実した物件がおすすめです。このように、2人の生活スタイルや将来の計画に合わせて優先順位を話し合い、納得のいく物件を選びましょう。 2人暮らしの初期費用の目安と抑えるコツ 2人暮らしを始める際の初期費用は、大きく分けて賃貸契約・引越し・家具家電の3つに分類されます。引越しや新生活にかかる費用を前もって確認し、計画的に貯金をしておくと、安心して2人暮らしを始められます。 初期費用の目安 賃貸契約の初期費用は、契約時にまとまって必要となる費用です。地域によっても異なりますが、一般的な内訳と目安は以下のとおりです。 ・敷金:家賃の1~2ヶ月分 ・礼金:家賃の1~2ヶ月分 ・仲介手数料:家賃の1ヶ月分 ・前家賃:入居月の家賃 ・共益費:入居月分 ・火災保険料:年間1万円前後 ・鍵交換費用:1~2万円程度 家賃8万円の物件の場合、少なくとも40万円の初期費用が必要となる計算です。引越し費用は時期や距離にもよりますが、15~25万円程度を見込んでおきましょう。2人分の荷物をそれぞれ運ぶため、単身の引越し2回分の費用がかかる点に注意が必要です。家具家電は、性能や大きさによって幅があります。新品でそろえると30~40万円程度かかることもありますが、すでに手元にある物や中古品を活用すれば大幅に抑えられます。 これらを単純に合計すると、80~100万円程度がかかることが見込まれます。 初期費用を抑えるコツ 高額になりがちな2人暮らしの初期費用を抑えるカギは、まず契約時期の選択です。一般的に3月~4月は引越しのピークシーズンで費用が高くなりやすい一方、10月~12月や平日を選ぶと、比較的安くなる傾向があります。 賃貸契約の初期費用は、物件の選び方や契約方法の工夫により節約が可能です。例えば敷金・礼金なしの物件を選ぶことで、家賃の2~4ヶ月分の費用を削減できます。また、部屋の設備や間取りが同じでも、場所や築年数によって家賃相場は大きく異なります。少しでも費用を抑えたい場合は以下のような物件や地域を視野に入れましょう。 ・駅から遠い物件駅から徒歩10分以内の物件は相場より高く、徒歩15分以上離れると安くなる傾向があります。 ・人気エリアから離れた場所複数路線が利用可能なターミナル駅周辺や商業施設が充実している地域も、相場より高くなりがちです。一駅離れるだけでも、家賃を数万円抑えられることがあります。 ・築年数が古い物件築年数が経つにつれて、家賃は下がる傾向があります。築年数10年以上でも、リノベーションやリフォームされていて、古さが気にならない物件もあります。 初期費用を抑えるならテレルーム 賃貸契約の際、通常仲介手数料は家賃1ヶ月分かかります。しかしテレルームなら、物件によって仲介手数料無料でのご案内も可能です。ぜひお気軽にご連絡ください。まずは話を聞いてみる 2人暮らしの前に確認しておくべきこと 2人暮らしを始める前に、お互いの希望や条件をしっかりと確認し合うことが、快適な生活を送るための最初のステップです。特に以下の点について、事前に話し合うことをおすすめします。 希望の家賃 家賃は毎月の大きな支出となるため、お互いの希望を事前によく話し合う必要があります。具体的な金額を決めておかないと魅力的な設備や間取りに惹かれ、予算オーバーしてしまいがちです。その結果、後々の生活を圧迫してしまう可能性があります。 初期費用の予算 初期費用の予算計画は余裕を持って立てることが大切です。特に、家賃の発生時期については注意が必要です。契約日と実際の入居日が異なる場合も多く、その期間の家賃も必要となります。また、引越し費用や家具家電の購入費用なども含めた資金計画を立てることで、安心して新生活をスタートできます。 譲れない条件 物件選びにおいて、それぞれの譲れない条件を明確にすることが大切です。設備やセキュリティ・周辺環境・通勤時間など、優先順位をつけて整理しましょう。内見はできるだけ2人で行くことをおすすめします。実際に家の周りや部屋を見て、具体的な生活のイメージを共有することで、入居後のミスマッチを防げます。 生活費の分担 生活費をどのように分担するかは、2人の収入状況や価値観に応じて決める必要があります。主な分担方法としては、全ての費用を半分ずつ負担する方法と、それぞれの収入に応じて負担割合を決める方法があります。分担方法は収入の変化や将来の貯蓄計画なども考慮しながら、柔軟に調整していきましょう。 生活スタイル お互いの生活スタイルの違いは、物件選びに大きく影響します。特に就寝時間や仕事のスケジュールが異なる場合は、それを考慮した間取り選びが大切です。例えば、パートナーが夜勤の場合、寝室とリビングを完全に分けられる間取りが望ましいでしょう。また、在宅ワークの頻度や趣味の時間の使い方なども、物件選びの重要な要素です。生活スタイルの違いは、些細なストレスの原因となる可能性もあります。お互いの習慣や好みを理解し、必要に応じて譲り合える部分を話し合っておくことで、より快適な2人暮らしを実現できます。 2人暮らしの賃貸は優先順位を決めて探そう! 2人暮らしの賃貸物件選びは、将来を左右する大きな決断です。この記事では、間取りの選び方から、家賃の目安・初期費用・物件選びの具体的なポイントまで詳しく解説してきました。単に広さや家賃だけでなく、通勤の利便性・周辺環境・将来の生活設計まで考慮した選択が必要です。 理想の賃貸を探すならテレルーム テレルームでは、お2人の希望に合った物件探しをサポートいたします。仲介手数料0円からの物件も多数ご用意していますので、まずはお気軽にご相談ください。まずは話を聞いてみる

-
同棲の初期費用は抑えられる!賢い物件選びや契約のコツも解説
2024.12.11同棲を検討されている方のなかには、初期費用にお悩みの方も多いのではないでしょうか。引越しするときは、二人分の費用が必要になるケースもあり、想定以上の出費になりがちです。しかし、賃貸契約方法や物件選びを工夫することで、初期費用を大きく抑えられます。この記事では、同棲時の初期費用の具体的な内訳から、実践的な節約方法まで詳しく解説します。今後、二人暮らしを考えている方は、ぜひ参考にしてください。 同棲の初期費用の目安 同棲を始める際の初期費用は大きく分けると賃貸契約・家具家電の購入・引越しの3つです。例えば家賃が8万円だった場合、賃貸契約で約40万円、これに家具家電の購入費用と二人分の引越し費用を合わせると100万円近くになることもあります。しかし特に賃貸契約の初期費用は、賢く物件を選び、契約方法を工夫することで抑えられます。まずは、賃貸契約に関わる初期費用の内訳を詳しく見ていきましょう。 同棲の賃貸契約で必要な基本費用 賃貸契約を結ぶ際には、必ず発生する基本的な費用があります。これらの費用は物件や地域によって異なるため、事前に確認しておく必要があります。 ・敷金:家賃の1~2ヶ月分 ・礼金:家賃の1~2ヶ月分 ・仲介手数料:家賃の1ヶ月分 ・前家賃:入居月の家賃 ・共益費:入居月分 ・火災保険料:年間1万円前後 ・鍵交換費用:1~2万円程度 契約前に必要な金額を確認し、しっかり準備しておきましょう。礼金が設定されていないケースもありますが、一般的には家賃の6倍程度は、初期費用として覚悟をしておくのが無難です。 同棲の初期費用を抑えるコツ:賃貸契約 二人暮らしの賃貸初期費用は以下のポイントを押さえて、賢く契約を進めていきましょう。 1.敷金礼金なし物件を探す 賃貸物件のなかには、敷金や礼金がない物件もあります。通常、敷金は家賃の1~2ヶ月分、礼金も1~2ヶ月分が相場ですが、これらが不要になると、初期費用を数十万円単位で削減できます。敷金礼金がない物件は家賃が若干割高になる傾向がありますが、1~2年程度の居住予定であれば、敷金礼金なし物件の方が経済的な場合が多いです。 2.仲介手数料を抑える 仲介手数料は家賃の1ヶ月分が上限と法律で定められていますが、複数の不動産会社で相見積もりを取ることで、半額や「仲介手数料0円」などの条件を引き出せる可能性があります。 3.フリーレント物件を活用する フリーレント物件は、契約開始後の一定期間(通常1~2ヶ月)の家賃が無料となり、実質的な初期費用の削減が可能です。特に新築物件や築浅物件で多く見られ、空室期間の長い物件でも導入されていることがあります。時期を選んで探すことで、条件の良い物件をお得に借りられる可能性が高まります。 4.連帯保証人だけで借りられる物件を探す 最近は保証会社の利用を必須とする物件も増えていますが、連帯保証人のみで契約可能な物件もあります。そのような物件を不動産会社に探してもらうことで、保証会社への初回保証料や年間更新料などの費用削減が可能です。これらの方法を組み合わせることにより初期費用を抑えられます。ただし、契約内容をしっかり確認し、後々トラブルにならないよう注意が必要です。また、初期費用を抑えすぎて住まいの環境が著しく低下するのは本末転倒なので、二人で暮らすうえでの快適さとのバランスを考えることも大切です。 費用をおさえたいならテレルームへ相談 テレルームなら、物件によって仲介手数料無料でのご案内も可能です。ぜひお気軽にご連絡ください。 まずは話を聞いてみる 同棲の初期費用を抑えるコツ:物件選び 初期費用は物件選びの段階で大きく変わります。特に同棲の場合は二人の通勤や生活環境を考慮しながら、賢く物件を選ぶことが重要です。以下の3つのポイントを押さえることで、同じエリアでも初期費用を抑えた物件選びが可能になります。 1.駅から少し離れた物件を選ぶ 駅徒歩10分以上の物件は、駅近物件と比べて初期費用が比較的安く設定されています。多少駅から離れていても自転車通勤が可能な場合は、積極的に検討してみましょう。実際、駅から徒歩10分以内と徒歩10~15分の物件を比べると、初期費用に20万円程度の差が出ることもあります。 2.築年数のある物件を検討する 新築物件は魅力的ですが、築5年以上の物件なら初期費用を大きく抑えられます。ただし、設備や間取りはしっかり確認し、二人の生活に支障がないか確認することが重要です。水回りの設備が新しければ、築年数が気にならない物件も多くあります。 3.人気エリア以外の物件を探す 人気エリアは便利である反面、初期費用が高額になりがちです。便利な急行停車駅やターミナル駅から一駅離れただけでも、初期費用に大きな差が出ることがあります。二人の通勤時間のバランスを考慮しながら、少し離れたエリアも視野に入れて探しましょう。生活のしやすさとのバランスは大切なので、実際に物件を見学して、二人で十分に話し合いながら決めることをおすすめします。 同棲の初期費用を抑えるコツ:引越し 同棲を始める際は、賃貸契約の初期費用に加えて引越し費用も必要です。二人分の荷物を運ぶため、単身の引越し費用が二人分必要となり、目安は15~25万円です。距離や時期によってはさらに高額になることもあります。このように引越し費用は高くなりがちな分、工夫次第で抑えられる額も大きくなります。以下の方法を可能な限り取り入れてみましょう。 1.時期の選択 引越し費用は時期によって大きく変わります。引越しのピークシーズンである3月と4月は避け、平日や月末を選ぶと費用を抑えられます。早朝など時間帯によっては、追加で割引が適用されることもあるので、サービス内容をよく確認しましょう。 2.見積もり比較 複数の引越し業者から見積もりを取ることも大切です。最低でも3社以上から見積もりを取り、料金を比較しましょう。最近はWEB割引を実施している業者も多いため、オンラインでの見積もり依頼がおすすめです。また、複数の引越しプランを比較検討することで、最適な料金プランを見つけられます。 3.不用品の整理 引越し前に断捨離することで、運ぶ荷物を減らせます。二人の持ち物を確認し、不要になったものは、リサイクルショップやフリマアプリを活用して処分するのがおすすめです。場合によっては、売って得たお金を引越し費用の一部に充てることもできます。このように、引越し費用も事前に計画を立てることで、賢く節約できます。初期費用と合わせて、計画的な準備を心がけましょう。 同棲開始までにすべきことをリストでチェック! 同棲を始めるまでには、様々な準備が必要です。計画的に進めることで、余裕を持って新生活をスタートできます。ぜひチェックリストとして活用してください。 3ヶ月前~1か月前までにすべきこと ・希望条件の整理と物件探し開始 ・初期費用の概算と貯金計画の開始 ・引越し時期の検討と仮決定 ・物件の内見と契約 ・初期費用の準備 ・引越し業者の見積もりと契約 ・必要な家具家電のリストアップ ・各種手続き(住所変更など)の準備 ・現住居の退去手続きの確認 転出届は引越しの2週間前から提出可能で、転居届は引越し後2週間以内の提出が必要です。 前日までにすべきこと ・必要な書類の最終確認と準備 ・荷物の梱包完了 ・新居の鍵の受け取り確認 ・引越し業者との最終打ち合わせ ・現住居の掃除 引越し後すぐに必要になるものは、段ボールにメモをしておくと便利です。 引越し当日にすべきこと ・引越し業者の立ち会い ・荷物の搬入場所の指示 ・電気・ガス・水道の開通確認 ・家具や家電の配置確認 ・現住居の最終確認と鍵の返却 前日と当日は特に慌ただしくなりがちです。必ずチェックリストを作成し、二人で確認しながら進めることをおすすめします。 同棲に必要な生活用品と費用目安 賃貸契約の初期費用を上手く抑えられたら、その分を生活用品の購入に回せます。特に家具や家電は単身用のものより価格が高くなるため、予算に余裕を持たせることが大切です。新生活に向け必要な生活用品と選び方のコツをご紹介します。必要なものと費用目安を確認しておきましょう。 必須の生活用品(優先度:高) ・冷蔵庫(20~30万円) ・洗濯機(5~10万円) ・電子レンジ(2~3万円) ・ベッド(10~15万円) ・エアコン(8~12万円) ベッドは二人で使用する場合、セミダブル以上がおすすめです。エアコンは設置されている物件もあるので、確認後に購入しましょう。 生活を快適にするもの(優先度:中) ・テレビ(5~10万円) ・食器棚(3~5万円) ・ダイニングテーブル(3~5万円) ・掃除機(2~4万円) どちらかがすでに持っているものを活用できると、初期費用を抑えられます。 あると便利なもの(優先度:低) ・ソファ(5~8万円) ・作業用デスク(1~2万円) ・インテリア類(1~3万円) ・収納家具(2~4万円) これらの生活用品は、一度に全てそろえる必要はありません。暮らしていくなかで必要かどうかを見極めて準備すると、不要な買い物を防ぎ費用を抑えられます。 同棲費用の分担方法 同棲での費用分担は、お互い無理のない分担方法を見つけることが大切です。最もシンプルな方法は、かかる費用を二人で均等に分けることです。ただし折半する場合、収入の差が大きいと、収入が低い方の家計を圧迫してしまう可能性があります。もう一つの選択肢は、収入比率に応じた分担です。例えば、月収30万円と20万円の場合、3:2の比率で分担することで、双方の負担感を公平に保てます。この方法では、お互いの経済状況に応じて無理なく生活設計できるのがメリットです。どちらの方法を選ぶにせよ、定期的に話し合いの機会を設け、必要に応じて見直すことが大切です。 同棲の初期費用を抑えるなら賃貸契約を工夫しよう! 同棲において、賃貸契約・家具家電・引越しなどの初期費用は、大きな課題となりがちです。しかし、この記事で紹介した方法を実践すれば、効果的に費用を抑えられます。二人の新生活を始めるにあたって、まずは賃貸初期費用の準備から計画的に進めていきましょう。 賃貸初期費用を抑えるならテレルーム テレルームは物件によって、家賃・エリア問わず、仲介手数料を0円に抑えることが可能です。理想の暮らしが実現できるよう、お二人の希望に合った物件探しをお手伝い致します。ぜひお気軽にご連絡ください。まずは話を聞いてみる
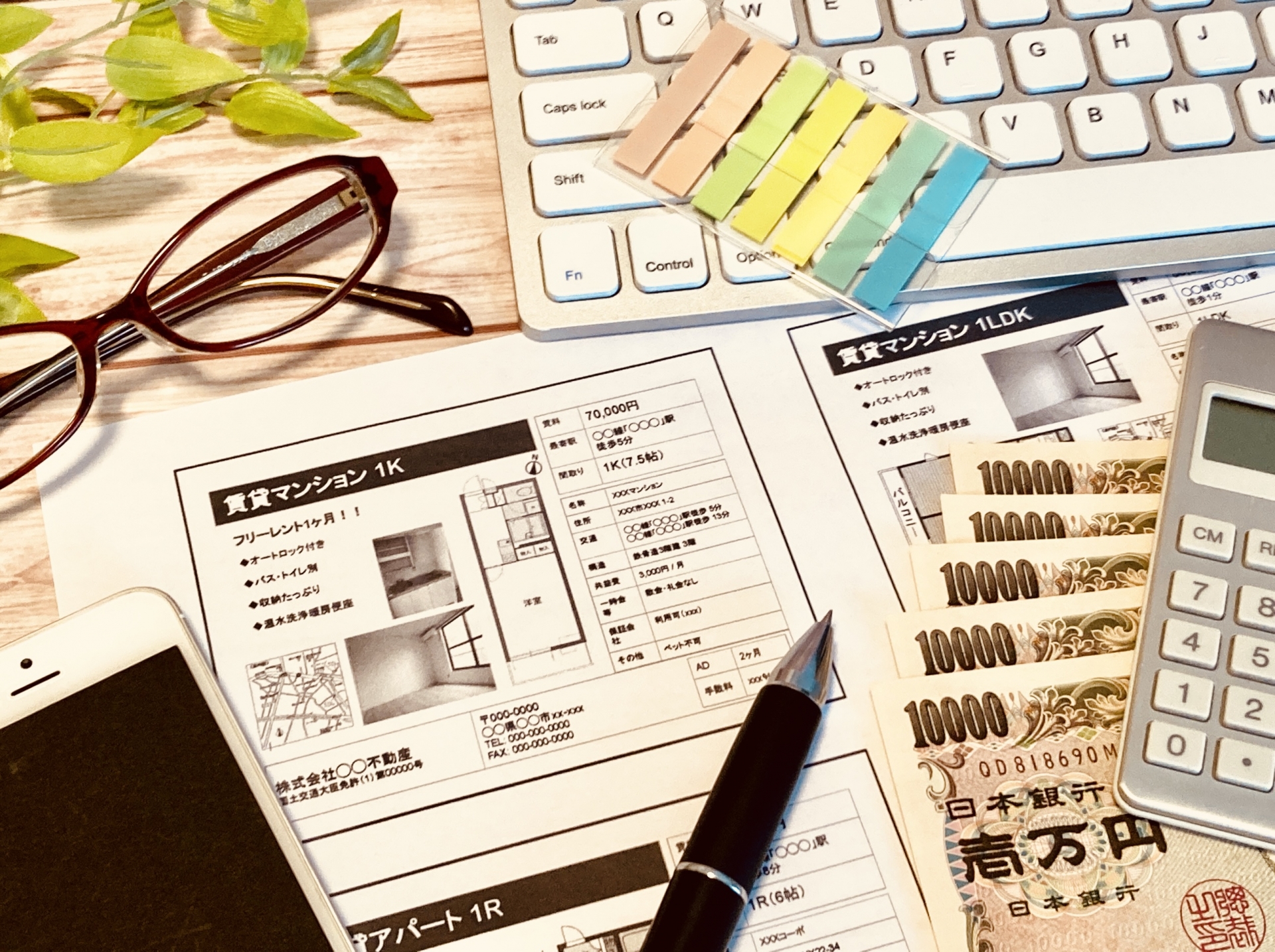
-
【お部屋探しの方必見!】仲介手数料を値引きするコツや安く抑える方法を紹介!
2024.11.14「仲介手数料を安くして引っ越したい」 「仲介手数料を安くする方法は?」 お部屋探しの際は、極力引っ越し初期費用を抑えたいところ。少しでも仲介手数料を安くしたいと考える方も多いのではないでしょうか。 そもそも仲介手数料はどれくらいが相場であるのか分からない方も多く、値引きすること自体可能であるのか分からない方もいらっしゃいます。 この記事では仲介手数料を値引きするコツと、交渉するタイミング、安くする3つの方法を紹介します。 仲介手数料は値引きすることはできる? そもそも仲介手数料は値引きすることが可能なのでしょうか。その点を踏まえ、仲介手数料の相場を紹介します。 仲介手数料は「家賃1か月分+消費税」が相場 仲介手数料の相場は「家賃1か月分+消費税」です。この金額は「国土交通省の告示」で定められた上限額です。そのため、家賃1か月分以上の仲介手数料は請求できないことになっています。 しかし、国土交通省の告示では上限額のみ定められており、下回る分に関しての制限はありません。そのため、不動産会社によっては仲介手数料を家賃の50%程に設定している会社もあります。 値引き交渉は可能 仲介手数料の上限は決められていますが、下限はないため、値引き交渉自体は可能です。 ただし、仲介業をメインとしている不動産会社の場合、仲介手数料は大事な収入源であるため、必ずしも交渉に応じてもらえるわけではありません。 また、大手の不動産会社になると、担当者に仲介手数料の目標が定められているケースが多いため、そもそも値引き対応していない場合もあります。 とはいえ、仲介手数料の値引き交渉は、不動産会社の立場とすれば日常茶飯事です。少しでも安くしたい方は、不動産会社に交渉してみましょう。 テレルームでは、仲介手数料が最大無料となっています。家賃1か月分と比較すると、引っ越し時にかかる費用を大きく圧縮することができるため、ぜひご活用くださいませ。 仲介手数料を値引きするコツ 仲介手数料を値引きするためには、「ただ安くしてほしい」と伝えるのではなく、以下の3つのコツを意識しましょう。 ・あらかじめ予算を決めておく ・閑散期にお部屋を探す ・他社の見積もりと比較する コツをつかんで交渉すると、うまく値引きできる可能性も高まります。一つずつ確認していきましょう。 あらかじめ予算を決めておく お部屋探しの相談をする際、あらかじめ予算を決めて伝えておくと、仲介手数料が安くなる可能性も高まります。 不動産会社としても、賃貸物件の入居を成約させたいと考えているため、なにかしら工夫をして予算内に収めようと協力してくれます。どの初期費用を抑えられるか検討し、仲介手数料を安くしてくれる場合もあります。 予算を伝える際は、事前に物件にかかる費用を把握しておきましょう。物件に引っ越しする際は、以下の項目の初期費用が発生します。 敷金家賃1か月分~2か月分礼金家賃1か月分~2か月分前家賃家賃1か月分火災保険料1年あたり約7,000〜約1.5万円鍵交換費用1.5万円~1.7万円仲介手数料家賃1か月分合計(家賃4か月~6か月分)+(2.2万円~3.2万円) 例えば家賃が10万円であれば、42.2万円〜63.2万円の初期費用がかかるということです。 もちろん、その他にも費用がかかるケースもありますが、上記のようにあらかじめ予算を確認して決めておけば、仲介手数料を値引きできる可能性も高まります。 仮に仲介手数料が安くならなくても、敷金や礼金などが低い物件を紹介してくれる場合もあるため、どちらにせよ初期費用を抑えることができるでしょう。 閑散期にお部屋を探す 閑散期である6月〜8月にお部屋探しをすると、仲介手数料の値引き交渉をすることができる場合もあります。 1〜3月・9〜10月の繁忙期は、不動産会社にとって仲介手数料の稼ぎ時であるため、交渉しても他の入居者が見つかることから交渉に応じてもらえない場合も多いです。 しかし、閑散期であれば、少しでも多く成約させたいと考えているため、値引き交渉ができやすくなります。 他社の見積もりと比較する 他の不動産会社の見積もりを提示すれば、値引き交渉できる可能性も高まります。他社の仲介手数料を提示すれば、額の比較ができるので交渉に応じてもらいやすいです。 テレルームでは、他社の仲介手数料が無料の場合、最大10万円のキャッシュバックキャンペーンを行っているため、どこよりもお得に物件を見つけることができます。 仲介手数料を値引きするタイミングは 仲介手数料の値引きタイミングはいつ行うべきなのか疑問に思う方もいらっしゃることでしょう。ここでは3つのタイミングを紹介します。 ・不動産会社へ相談する時 ・部屋を決めようとする時 ・遅くても審査後までに行う 一つずつ確認していきましょう。 不動産会社へ相談する時 不動産会社へ相談する時、初期費用の予算を伝えておきましょう。多くの方は、間取りや立地、家賃などの希望条件のみを伝えがちですが、事前に予算を伝えておけば、不動産会社の担当者も金額面を考慮した物件を紹介してくれます。 値引き交渉は人によっては「言いづらい」「嫌がられるのでは」と考える方も多いです。しかし、事前に予算を伝えておけば、仲介手数料の値引き交渉もせずに済みます。 部屋を決めようとする時 部屋を決めようとする際、「仲介手数料がもう少し安ければ決めます」と伝えるのも値引き交渉をするタイミングの一つです。 もちろん過度な値引きは難しいかもしれませんが、不動産会社としても成約をさせたいため、交渉に応じてくれる場合もあります。 物件の内見を完了させ、見積もりを確認した時に伝えるようにしましょう。 遅くても審査後までに行う 仲介手数料の値引き交渉は、どれだけ遅くても審査後までに行うようにしましょう。審査がクリアした後は、契約手続きに移行します。 一般的には、入居審査が通った後にキャンセルするのは好ましくありません。もちろん賃貸契約書を締結していなければキャンセルすることは可能ですが、契約直前に値引き交渉をすると、トラブルに発展する可能性もあります。 審査の結果が出た段階で、すぐに値引き交渉をするようにしましょう。 仲介手数料を安く抑える3つの方法 仲介手数料を値引きするコツや交渉タイミングをお伝えしましたが、「交渉するのが苦手」という方もいらっしゃることでしょう。 そこで、ここでは交渉せずに仲介手数料を抑えることができる3つの方法を紹介します。 ・家賃の安い物件を選ぶ ・AD物件を狙う ・仲介手数料が安い不動産会社を選ぶ ひとつずつ詳しく紹介します。 家賃の安い物件を選ぶ 家賃の安い物件を選べば、仲介手数料を抑えることができます。仲介手数料は家賃の金額に反映されるため、必然と安く済ませることができます。 さらに、敷金や礼金などの価格も、家賃がベースとなっているため、初期費用のトータルを抑えることが可能です。 例えば家賃10万円の物件より家賃8万円の物件では、以下の表の通り初期費用が安くなります。 家賃10万円家賃8万円敷金(家賃1か月分)10万円8万円礼金(家賃1か月分)10万円8万円前家賃(家賃1か月分)10万円8万円火災保険料(1.5万円)1.5万円1.5万円鍵交換費用(1.7万円)1.7万円1.7万円仲介手数料(家賃1か月分+消費税)11万円8.8万円合計44.2万円36万円 比較してわかる通り、上記のケースでは約8万円近く費用を抑えることができます。抑えた金額は家具家電などの費用に回すことも可能です。 AD物件を狙う AD物件であれば、仲介手数料が安く設定されているケースもあるため狙い目です。 AD物件とは、大家が不動産会社へ広告費を支払っている物件のことです。入居者にとっては、賃貸の初期費用はひとつのネックポイントです。 そのため、大家は不動産会社へ広告費を支払い、その分、仲介手数料を入居者からもらわないという仕組みで入居者の負担を抑えています。 AD物件は、入居者へ仲介手数料を請求しないケースが多いため、AD物件を狙えば仲介手数料を抑えることができます。 もちろん不動産会社によって請求の有無は異なるため、一概には言えないものの、テレルームではAD物件に関しては仲介手数料を0円に設定しております。 仲介手数料が安い不動産会社を選ぶ 値引き交渉が苦手な方は、仲介手数料が安い不動産会社を選ぶようにしましょう。仲介手数料は「家賃1か月分+消費税」が相場であり上限とされておりますが、安く設定している業者も多いです。 仲介手数料を家賃55%に設定したり、一律金額に設定している不動産会社も多いです。 そのため、わざわざ値引き交渉をする必要もなく、仲介手数料を抑えることができます。 とはいえ、仲介手数料が安いと手数料以外の費用がかかる可能性もあります。部屋の消毒代や鍵交換費用、退去時のクリーニング代などで初期費用が嵩んでしまう可能性もあるため、トータルの見積もりを出してもらっておきましょう。 仲介手数料が安い不動産会社を探している方は、「仲介手数料が安い不動産会社はどこ?仲介手数料を安くする方法と不動産会社を選ぶ際の注意点を解説!」を参考にしてください。 また東京都内の物件をお探しの方であれば「東京で仲介手数料が安い不動産会社10選!賃貸物件を探すときの注意点も解説」でもご紹介しております。 まとめ 仲介手数料は「家賃1か月分+消費税」が相場ですが、値引き交渉することはできます。あらかじめ予算を伝え、閑散期などにお部屋探しなどをすることで、交渉がうまくいく可能性も高いです。 とはいえ、必ず値引き交渉がうまくいくわけではないため、もともと仲介手数料が安い不動産会社に相談するのも一つの選択肢です。 テレルームでは、仲介手数料が最大無料と設定しておりますので、他社より安い初期費用で引っ越しができます。 初期費用を抑えて引越しをしたいという方は、ぜひ一度ご相談くださいませ。