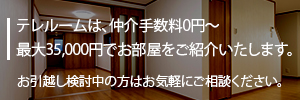親族が所有していた土地や建物を相続するのは、多くの方にとって初めての経験となるはずです。大切な家族の不動産を、どのように引き継げばいいのか不安に感じることは少なくありません。
この記事では、不動産を相続する際の名義変更の期限や相続不動産の分け方、手続きの流れをわかりやすく解説します。不動産の手続きを放置して、権利関係が複雑化しないためにも、最後までお読みください。
※本記事に記載されている内容は、2025年7月執筆時点のものです。記事公開以降に、法改正される可能性もありますので、最新情報は法務局や法務省などのホームページなどでご確認ください。
目次
不動産を相続するときの名義変更はいつまで?
不動産の所有者が亡くなったときに所有権を相続人に移転する相続登記は、2024年4月1日から義務化されました。相続登記の期限は、その不動産の所有権を知った日から3年以内です。期限内に登記できなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記をしないままでいると、相続人が亡くなることによって相続人が増え、権利関係が複雑になるかもしれません。不動産を相続するときは、できる限り早めに手続きを進めることをおすすめします。
参考:不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~ | 法務省
不動産を登記申請する流れ
相続する不動産の手続きは、次のような流れで進めます。
・遺言書を確認する
・相続人を調べる
・財産を調査する
・遺産分割協議を行う
・不動産の登記を申請する
それぞれの手続きを見ていきましょう。
遺言書を確認する
まず、亡くなった被相続人が遺言書を残しているかどうか確認しましょう。遺言書には、財産を誰にどのように分けるかについて、被相続人の意思が示されています。
遺言書が見つかった場合、その内容に従って相続手続きを進めるのが原則です。一方で遺言書がないときは、親族内で遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは、相続人全員で、遺産を誰がどれだけ受け継ぐかを話し合って決めることです。
相続人を調べる
次に、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本を取り寄せ、相続人を確定させます。相続人調査に漏れがあると、遺産分割協議をやりなおすことになるため、法律で定められた相続人の範囲を正しく把握しましょう。
2024年3月から、戸籍謄本は本籍地以外の市役所でも請求できるようになりました。たとえば大阪府に本籍がある被相続人の戸籍を、東京都の役所で請求できます。
参考:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) | 法務省
財産を調査する
不動産や預貯金、株式などのプラスの財産と、借金や未払金といったマイナスの財産である負債の両方を調査し、すべて洗い出します。
不動産は、登記事項証明書や固定資産税の納税通知書などを確認して、所有しているかどうか調べてください。預貯金や株式は通帳や証券、金融機関から届いた書類で確認できます。
遺産分割協議を行う
遺言書がないときや遺言書があっても相続人全員の同意があるときは、遺産分割協議を行います。不動産や預貯金などのすべての財産の分け方を、相続人全員で話し合います。
話し合いがまとまったら、内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名・捺印してください。
不動産の登記を申請する
登記申請は、不動産の所在地を管轄する法務局で行います。書類の準備や手続きは複雑なため、司法書士に依頼するのが一般的です。司法書士は、必要書類の準備から登記申請まで、手続き全般を代行してくれます。
不動産を相続するときの分割方法
遺言書がなく、複数の相続人がいるときの不動産の分割方法は原則として話し合いで決められます。不動産の分割は、主に次の3つの方法があります。
現物分割
現物分割は、相続した不動産をそれぞれの相続人がそのままの形で受け継ぐ方法です。複数の不動産がある場合、Aさんは自宅の土地と建物を、Bさんは別の土地というように個々の不動産をそれぞれの相続人が所有します。
あるいは、広大な土地であれば、それをいくつかの区画に分けて、それぞれの相続人が所有するケースも現物分割に当たります。
現物分割のメリットは不動産を売却したり、現金化したりする必要がないため、手続きがシンプルかつ売却にかかる費用や税金を抑えられる点です。
しかし、それぞれの不動産の価値が異なるときは、公平に分けるのが難しいデメリットがあります。相続人全員が納得できるように、不動産の評価額を正確に把握し、話し合いを重ねましょう。
代償分割
代償分割は、特定の相続人が不動産をすべて受け継ぎ、その代わりとして、他の相続人に対して現金を支払う方法です。たとえば、長男が被相続人の名義の家に住み続けたいケースでは単独で相続し、建物の価値に相当する現金を他の相続人に支払います。
代償分割のメリットは、不動産を分けずに一つの不動産として活用できることです。分割が難しい一戸建ての家を相続するケースに適しています。
一方で、不動産を受け継ぐ相続人には、他の相続人に支払う代償金を用意する経済的な負担が発生します。代償分割をするときは代償金をどのように準備するか、事前に計画を立ててましょう。
換価分割
換価分割は、相続した不動産を売却し、その売却代金を相続人全員で分ける方法です。不動産そのものではなく、現金として分割するため、最も公平な分割方法と言えるでしょう。
メリットは、相続人全員が公平に財産を受け取れる点です。不動産の価値に差があっても、売却してしまえば公平に現金として分けられます。また、特定の相続人が現金を用意する負担もありません。
しかし、売却にかかる仲介手数料や登録免許税などの費用、売却益が出た場合には譲渡所得税がかかるり、手元に残る財産が少なくなります。売却のタイミングや価格設定を相続人全員で話し合って決めるため、他の方法に比べて時間がかかる可能性があります。
マンションの売却を検討している方は、こちらの記事をご覧ください。
マンション売却の準備から引渡しまで徹底解説|高く・早く売るためのコツもご紹介!
テレルームなら相続した不動産の売却をサポート
相続した不動産を売却して、現金化して分割したいと考える人もいるかもしれません。もし、相続した不動産の売却を検討しているなら、テレルームが全面的にサポートします。
テレルームは、相続不動産の売却に関する豊富な実績と専門知識を持つプロフェッショナルです。相続に関する複雑な状況も考慮しながら、それぞれのステップで適切なアドバイスとサポートを提供します。スムーズに不動産を現金化をするためにも、まずはテレルームにご相談ください。
不動産を相続するときの注意点
不動産の相続手続きを後回しにしたり、分割方法を間違えてしまうと、親族間のトラブルにつながりかねません。ここからは、円満に相続するためにも、気をつけたいポイントを解説します。
不動産を共有で相続しない
共有とは、一つの不動産を複数の人が所有することです。たとえば、被相続人名義の生まれ育った家を兄弟2人の共有名義にするようなケースです。
共有名義にすると、売却やリフォーム、賃貸に出すなど、その不動産に関して行動を起こす際には、原則として共有者全員の同意が必要になります。
将来的に意見が食い違ったり、連絡が取りにくくなったりすると、不動産の管理や処分が難しくなります。可能であれば、不動産を相続するときは現物分割や代償分割をしましょう。
早めに相続手続きを進める
相続登記をしないままでいると、不動産の名義が被相続人のまま残り、売却や担保設定などの所有者としての権利を行使できません。
また時間が経つにつれて、相続人がさらに亡くなったり、連絡が取れなくなったりして、権利関係が複雑になる可能性があります。遺産分割協議がまとまりにくくなり、手続きが難しくなります。
余計な手間や費用、トラブルを避けるためにも、相続が始まったらできる限り早い段階で司法書士をはじめとした専門家に相談し、手続きを進めましょう。
不動産の相続登記にかかる費用
相続した不動産の登記を行う際には、以下のような費用がかかります。
費用 | 概要 |
|---|---|
| 登録免許税 | 不動産の評価額に応じてかかる税金。原則として、税率は不動産の固定資産評価額の0.4%。 |
| 司法書士報酬 | 依頼する内容や不動産の数、難易度によって異なるが、数万~数十万程度。 |
| 実費 | 書類取得費用、郵送費用など |
上記の費用は、相続する不動産の数や評価額、手続きを任せる専門家によって変動します。金額が気になる方は、事前に司法書士に見積もりを依頼しましょう。
不動産の相続登記を申請するときの必要書類
不動産の登記を申請する際には、以下のように多くの書類が必要になります。
・戸籍謄本
・住民票
・遺言書または遺産分割協議書
・固定資産税の評価証明書
・印鑑証明書(遺産分割協議書を提出するときのみ)
戸籍謄本は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍と相続人全員の現在戸籍を提出してください。提出する住民票は、被相続人と不動産の新所有者になる方のものです。なお状況によって必要書類は異なるため、法務局に確認しましょう。
参考:相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等 | 法務局
不動産を相続するときの相続税の計算方法
相続税の申告と納税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内に行う必要があります。相続税の基本的な計算方法を理解し、課税されるのか確認しておきましょう。
相続税の計算式
不動産を含む相続財産全体が基礎控除額を超える場合に、相続税がかかります。相続税の基礎控除は、以下の計算式で求めます。
相続税の基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
法定相続人が3人の場合、基礎控除額は 3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円です。このケースでは、相続財産の総額が4,800万円以下であれば相続税はかかりません。
土地・建物の評価方法
相続税を計算するときの不動産の評価額は、不動産を売却するときの価格とは異なり、土地と建物それぞれで計算します。土地は、路線価方式または倍率方式で評価します。
評価方式 | 概要 |
|---|---|
| 路線価方式 | 路線価とは道路に面した土地の1㎡あたりの評価額。路線価に土地の面積や形状、間口の広さなどを考慮して計算する。 |
| 倍率方式 | 固定資産税評価額に一定の倍率をかけて計算する。 |
倍率方式は、路線価が設定されていない地域に適用されます。
建物の評価額は、原則として固定資産税評価額と同じです。固定資産税評価額は、毎年送られてくる固定資産税の納税通知書で確認できます。
特例や減額措置が適用される場合もあるため、正確な税額が気になる方は税理士に相談してください。
まとめ
相続登記は義務化され、その所有権を知った日から3年以内に手続きをする必要があります。
相続不動産の分割するときは現物分割、代償分割、換価分割の3つから、相続人全員の同意を得られる方法で手続きを進めてください。不動産を複数人で共有する方法は、将来のトラブルにつながる可能性があります。
相続した不動産の売却を考えている場合は、実績のある不動産会社に依頼しましょう。
相続した不動産の売却ならテレルームにお任せ
相続した不動産を売却して、相続人同士で公平に分けたいと考えているなら、テレルームにお任せください。
テレルームは、相続不動産の売却に関する豊富な経験と専門知識を持つプロです。不動産売却に関する知識が少ない方に対しても、丁寧にサポートいたします。
スムーズな売却を実現するために、まずはテレルームに相談してみませんか。